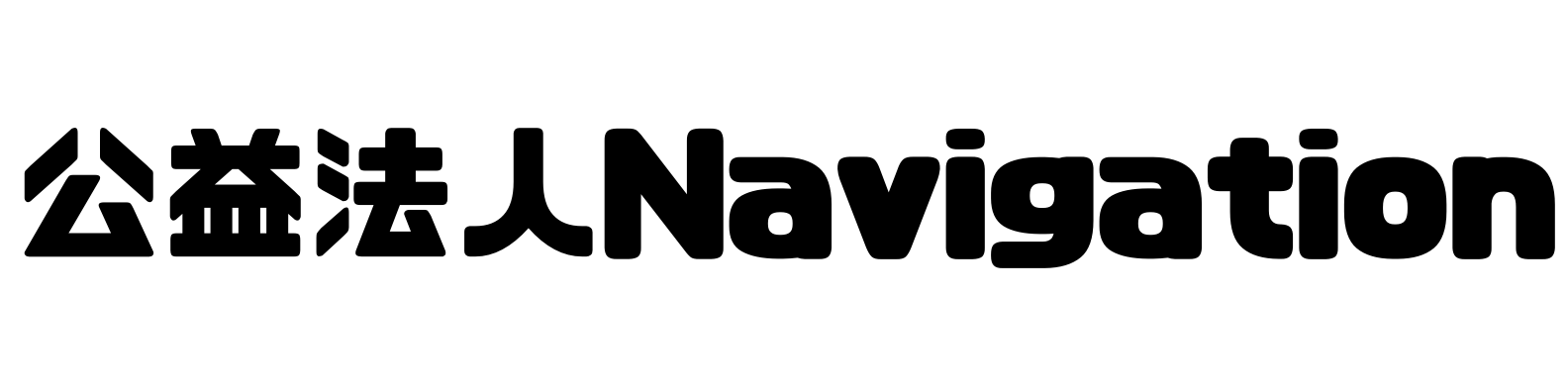公益法人Navigationを読んでいただきありがとうございます。公認会計士・税理士の大下航です。
この度、公益法人制度に関する重要な法改正があり、2025年(令和7年)4月1日より施行されました。
この記事を見られた方の中には「公益法人法の改正は大まかに知っているが、実務上どう対応すべきか不安」「そもそも公益法人法の改正内容を理解していない」「公益法人法の改正内容を確認したい」といった方々が多いと思います。
情報が少ない状況で施行された大きな改正なので、現場では実務上の対応について心配があるのではないでしょうか。
実際、この記事を書いている時点において実務上、若干手探り状態の部分が多少あります。
今回の公益法人法の改正は、実務上非常に大きなインパクトがあり、会計上は勿論のこと、法人運営上も対応が必要です。
改正内容を知らず以前と同じように公益法人を運営していると、法令違反として社会的信頼を失う可能性がある重要な改正なので、本記事をとおして改正ポイントをしっかりおさえましょう。
本記事では、改正内容が公益法人運営にどのような影響を与えるのか、実務的な視点から分かりやすく解説していきます。
1. はじめに
2008年(平成20年)12月に施行された新公益法人法から、今回の2025年(令和7年)4月改正まで16年以上が経過し、その中で様々な問題点が浮き彫りになり議論がされてきました。
今回の法改正は、公益法人のガバナンス強化の他、より柔軟で円滑な事業運営を目的としています。
実務上への影響としてはガバナンス強化、会計処理(表示方法)変更、定期提出書類のフォーマット変更、などへの対応として一時的に手間がかかるものの、全体としては法人運営上の柔軟性が高まりこの16年間で発生した問題点を解決する改正です。
より公益法人の自律した運営を期待された法改正ともいえますが、そもそも公益法人は社会貢献という大きな使命を果たすため、常に時代の変化に対応していく必要があります。
本記事を通じて改正内容を正しく理解し、皆様の携わる公益法人の運営に活かしていただければ幸いです。
2. 改正のポイントと詳細
2025年(令和7年)4月の公益法人法の改正は、旧制度における問題点を解決し、公益法人がより柔軟かつ効率的に活動できるようになることを目指す趣旨であると解釈できます。
そのような改正の根本にある趣旨・背景を念頭においたうえで、大きく分けて3つのポイントに分けて改正内容をみていくと、違和感なく改正内容がおさえられるでしょう。
特に、これまで公益法人の実務に携わる中で「公益法人はこの制限があるから面倒」と感じていた方にとっては、その制限が緩和される感覚があるのではないでしょうか。
改正のポイント
今回の改正の主なポイントは以下の3点です。
この3つのポイントは私が考えた分類ではなく、この度の改正において内閣府が作成しているパンフレット等にも記載された文言そのもので、公益法人法の改正を説明する際には必ず使われている文言なので、目にした方も多いのではないでしょうか。
この3つのポイントで分類したうえで、それぞれのポイントについて掘り下げていくことで、この度の改正を網羅的におさえることができます。
制度改正のポイント
- 財務規律の柔軟化・明確化
- 行政手続の簡素化・合理化
- 自律的ガバナンスの充実と透明性向上
それでは、以下で3つのポイントそれぞれの視点から改正内容について詳しく見ていきましょう。
改正のポイントをそれぞれ解説
まずはじめに、改正内容の実例や実務対応については、以下の解説中においてリンク先を用意し、そのリンク先からとぶ別ページの記事をご参照頂ければ掘り下げていくことができるようにしていきます。
よって、この記事は2025年(令和7年)4月に施行する公益法人法の改正内容のインデックスや目次として、もしくは、改正内容の全体概要や大枠をおさえる入口として読んで頂けると幸いです。
私の記事作成スピードが遅いので、この記事を読まれている方のタイミングによっては部分的にしかリンクが存在しない状況かもしれませんが、追々充実させていく予定ですのでご了承ください。
(1) 財務規律の柔軟化・明確化
改正前は、原則として毎事業年度の収支相償が求められたうえ、保有する財産についても厳格な制限が課されていました。
それに対して今回の改正で、以下の点が変更されました。
- 中期的な収支均衡へ
単年度ごとの収支相償ではなく、5年間という中期的スパンで収支の均衡を図ることが可能になりました。 これにより、公益目的事業の拡大や新たな事業への投資がより柔軟に行えるようになります。
実務上、この単年度における収支相償が公益法人の財務基準の最も悩ましい部分でした。
理由としては、収支相償の判定について「原則的には単年度で収支相償の判定としたうえ、収支の赤字については繰り越せない一方で黒字となった場合は繰り越して翌期に解消すべし~」という制限が公益法人の長期的な財政状況を圧迫する要因であったからです。
以前より財務担当の方から「収支相償をクリアしていたら公益法人は先細りで、いつか資金が無くなるんじゃないでしょうか?」という質問を受ける事が多々ありました。
その際には長期的な計画をたてたうえ「特定費用準備資金」や「特定資産取得資金」を上手く使って、毎事業年度何とか工夫して収支相償をクリアしていくことをすすめていました。
とはいえ、なかなか運用が難しかったため、今回の改正は現場の声をしっかりと反映した制度改正という印象です。
この「特定費用準備資金」「特定資産取得資金」についても改正があり、下記につながりますので合わせておさえましょう。
- 公益充実資金の創設
公益法人の将来における活動拡大のために積み立てておくことができる「公益充実資金」が創設されました。
これは従来の特定費用準備資金と資産取得資金が統合されたうえ、より資金活用の柔軟性を高めた資金として名称を「公益充実資金」としたものです。
これにより、寄附金や収益事業から得た資金は勿論、公益事業により発生した資金などを活用した機動的な事業展開や投資が可能になります。
単年度の収支相償を求めず5年という中期で収支均衡が求められるようになった~という説明を先ほどしましたが、この公益充実資金は長期的な運用が可能で、中長期的な観点からの改正といえるでしょう。
よって、中期的には収支均衡としたうえで、長期的には公益充実資金を利用して財務をコントロールすることが可能となりました。
- 公益目的事業継続予備財産の創設
保有制限の対象となる遊休財産(口述しますが改正法では使途不特定財産)のなかでも、保有制限の対象から除外することができる「公益目的事業継続予備財産」が創設されます。
この「公益目的事業継続予備財産」は緊急時に備えて法人が保有することができる財産です。
つまり法人が不測の事態に備えておくべき資金など、必要な範囲で財産を確保しやすくなりました。
旧制度時代において関与先の財務担当理事の方から
「遊休財産の保有上限をクリアするために特定資産を活用したいが、その特定資産はこの内容で大丈夫でしょうか?」
等と質問され、いざその特定資産の内容を拝見すると、将来の計画は未定で単に非常事態に備える趣旨の特定資産であるため控除財産とならない(つまり遊休財産の判定にあたり影響がない特定資産となってしまう)事例が多々ありました。
それに対して今回の改正で「公益目的事業継続予備財産」ができたことにより、遊休財産(以下で解説する使途不特定財産)の制限を気にせず災害やパンデミックなどの緊急事態にも対応できる資金を確保し、安定した法人運営をすることが可能となったのです。
- 遊休財産が使途不特定財産に変更
単純に名称の変更です。
「遊休財産」が「使途不特定財産」という名称になったとご理解ください。
この変更は「遊休財産」という名称があまりに誤解を招きやすいための変更です。確かに無駄な財産を公益法人が所有している~なんて思われそうな文言なので、もっともな変更と感じました。
- 遊休財産(使途不特定財産)の保有上限の変更
従来は1年間に発生する公益目的事業費が遊休財産(使途不特定財産)の保有上限額とされていました。
それに対して今回の改正で、遊休財産(使途不特定財産)の保有上限額が原則として、前事業年度までの過去5年間の各事業年度の公益目的事業費相当額の平均額となります。
収支相償が単年度ではなく、中長期における収支均衡となった改正との整合性をとったとご理解ください。
(2) 行政手続の簡素化・合理化
事業環境の変化に柔軟に対応できるよう、行政手続きが簡素化されました。
- 軽微な変更等が届出に
事業目的の変更を伴わない、軽微な定款変更(名称変更や事務所所在地変更など)や事業変更等については、これまでの行政庁の「変更認定」が不要となり、「変更届出」のみで済むようになりました。これにより、手続きにかかる時間と負担が大幅に軽減されます。
この「変更認定」と「変更届出」は似ているのですが実務上の負担は大きく違います。
詳しくはこちらの「2025年(令和7年)4月施行 改正公益法人法(公益認定法)対応「変更届」「変更認定届」」という記事で、公益法人法の改正に対応して実務を解説しているのでご参照ください。
(3) 自律的ガバナンスの充実と透明性向上
冒頭に公益法人法の改正は3つのポイントがあるとご案内しました。
繰り返しになりますが、この1~3です。
1.財務規律の柔軟化・明確化
2.行政手続の簡素化・合理化
3.自律的ガバナンスの充実と透明性向上
ここまで解説してきた1、2の内容は全て、従来の公益法人法の制限を柔軟化・簡素化した改正内容でした。
それに対して以下で解説する3つ目のポイントである「自律的ガバナンスの充実と透明性向上」は従来の公益法人法の定めより、一段階高いレベルのものを求める改正です。
言い方を変えれば、従来より公益法人の事務的な手間が増え負担となり得える一方で、やるべき事を押さえてしっかり対応しないと公益法人法改正への対応に不備が発生する事態につながります。
いずれも公益法人の信頼性を高めるための改正で、公益法人によっては事務的負担が急増するため計画的に対応することをおすすめします。
特に対応初年度においては混乱が発生する可能性があるので、公益法人内での事前調整が重要。
負担が増える大変さはありますが、結果としてガバナンスが高まり、公益法人にとって意義ある仕組みとなるよう対応を進めましょう。
- 外部理事・外部監事の設置義務化
すべての公益法人において、外部の理事・外部監事をそれぞれ1名以上置くことが義務付けられました。
これにより、法人内部の意見だけでなく、外部の視点を取り入れた公正な経営判断、透明性とガバナンスの強化が期待されます。
公益法人は主務官庁の管理下で公益性を担保されてるものの、事業に関連するメンバーによってある程度クローズドな組織で運営されていました。
イメージとしては、株式会社の中でも上場会社がより高いガバナンスを求められた結果、外部役員の設置が義務付けられたのと同じ流れです。
今回の公益法人法の改正では、公益法人の利害関係者が全国民である以上、ガバナンスをより強化し透明化を図るべく外部の役員を入れることとなりました。
実務上、この外部理事・外部監事を設置することについて、非常に多くのご質問やご相談を頂いておりますので別の記事でご紹介します。
- 会計監査人設置義務の拡大
会計監査人の設置義務の基準が、これまでの
「負債が50億円以上 又は収益・費用・損失が1,000億以上の場合に設置」
から
「負債が50億円以上 又は収益・費用・損失が100億円以上の場合に設置」
に引き下げられました。
これにより、より多くの法人が外部の独立した専門家である会計監査人による監査を受けることになり、結果として財務の信頼性が向上します。
今回の改正で会計監査を受けることになる公益法人にとって、会計監査人へ対して支払う会計監査報酬の負担、会計監査に対応する業務負担が増えるため、かなりの大きなインパクトとがある改正といえでしょう。
上記のような負担から、会計監査を受けることについてネガティブなイメージが強いと思われます。
しかし、会計監査を受けるにあたって、ただその都度現場レベルで監査人の指摘に対応するのみとせず、監査対応も組織として対応することで、外部的な視点を基に財務体制を含む内部統制の強化を図ることができます。
よって、会計監査人からの指摘を法人のガバナンス強化の糧とすることで、会計監査を法人にとってポジティブなものにしていくことをおすすめします。
- 会計処理において3区分経理が原則義務化
この度の公益法人法の改正により、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3区分経理が原則的に義務となりました。
この改正は言葉で表すとあっさりしたものですが、現場における経理上の負担はかなり増大することが見込まれます。
従来はフローを表す正味財産増減計算書についてのみ3区分の分類を求めていましたが、今回の改正では、ストックを表す貸借対照表についても3区分の分類を求めています。
貸借対照表にまで3区分を設けて表示することで、公益法人における財産の増減に状況をより透明にすることを目的としており、かつ、各事業の財務収支を明確にすることで、外部からの監視を受けやすくします。
従来、貸借対照表の3区分は一定の条件を満たした一部の公益法人のみの適用とされ、多くの法人が作成していませんでした。
今回の改正で貸借対照表内訳表に相当する計算書類を財務諸表の注記として記載することとされたのです。
この点について詳しくは別の記事で解説したいと考えておりますので、詳細は別の記事をご参照お願いいたします。
- 正味財産増減計算書が活動計算書となる
正味財産の増減を明らかにする書類として、従来は正味財産増減計算書がありましたが、正味財産増減計算書の作成は不要となります。
代わりに正味財産の増減を明らかにする書類としては、活動計算書の作成が必要となります。
単に名称が変わっただけではなく、様式が大きく変わりました。
注記も従来と大きく変わりましたので、上記の3区分経理と合わせて全ての公益法人が対応が必要な改正といえるでしょう。
3区分経理と同様に、決算書における様式が変更するということは、日々の伝票、稟議・承認申請、会計処理の内容、全てにおいて改正法へ対応することが求められます。
現場においては移行年度における事務負担が増えることで、決算シーズンに混乱が発生するリスクがあるため特に心配です。
しっかり準備を進めて対応してください。
詳しくは別の記事で解説を予定しておりますので、詳細は別の記事をご参照お願いいたします。
3. 全般的な実務への影響と対応策
繰り返しになりますが今回の法改正は、公益法人のガバナンス強化と効率的な運営に資するものです。
皆様におかれましては、少なくとも以下の4つの点を確認し適切に対応を進めてください。
- 定款・規程の見直し
- 外部理事・外部監事の設置義務化、また場合によっては会計監査人設置に対応するため、定款の見直しや役員規程・選挙規程などの整備が必要です。
- 決算に関連する計算書類、積立資金の名称が変更されているので、定款等に記載されている文言が旧法の文言である場合はアップデートが必要です。
- 中期事業計画の策定
- 財務規律の柔軟化を活用するため、中期的な視点での事業計画や予算計画の策定が重要となります。
- 公益目的事業継続予備財産と公益充実資金の活用を検討しましょう。
- 情報公開体制の強化
- 行政庁に提出された報告書類が原則として公開されるため、情報公開の体制を強化し、市民からの信頼確保に努めましょう。
- 公開情報となる書類の中に個人情報が含まれていないか、含まれている場合はどうマスキングするか確認しましょう。
- 会計基準の変更への対応
- 正味財産増減計算書から「活動計算書」への移行と3区分経理が、2028年4月1日から義務化されます(2025年4月1日~2028年3月31日の3年間は経過措置があり旧基準によることも可能)ので、早めの情報収集と対応準備を進めましょう。
- 会計ソフトの新基準対応時期と、実務上どの年度から新基準で経理処理を行うべきか、確認したうえで移行する必要があります。
4. まとめ
2025年4月1日施行の法改正は、公益法人の運営に大きな影響を与えるものです。特に、財務規律の柔軟化は、公益目的事業の拡大にとって追い風となるでしょう。
一方で、外部理事・外部監事の設置や情報公開の強化など、ガバナンス体制の整備がこれまで以上に求められます。
また、その一環で正味財産増減計算書が活動計算書となるうえ、原則3区分経理が必要となったのは、公益法人の経理担当者の方々にとって大きな負担増ではないでしょうか。
公益法人Navigationでは、今後も改正法に関するQ&Aや実務事例などを随時更新していく予定です。
この記事を読んでくださっている公益法人の理事・監事及び事務局皆様による健全な法人運営を心より応援しております。